本日のブログは、ドラマーの足のジストニアについての考察です。
ドラマーの足のジストニア(バスドラム)の一部を予防するのに、筋トレが有効である可能性について語ってみたいと思います。
ドラマーの筋トレ議論は、トッププロの中でも必要派と不用派に意見が分かれるところです。
必要派の意見としては、筋肉をつけることで音量を出しやすくなる、筋持久力がついて長時間のライブも楽に演奏できるようになる等が挙げられます。不用派の意見としては、演奏に必要な筋力は演奏することで身に付くので、無駄な筋肉をつけることで体が重くなり疲労しやすくなるなどが挙げられますし、トッププロには華奢な女性ドラマーも多数いらっしゃいます。
私個人の意見としては、楽器演奏に必要な筋力は演奏することで身に付くので、演奏以外の方法での筋トレは基本的に不用で、音量を出したければPAエンジニアに協力してもらうのが良いと思っておりますが、「一部のドラマーさんには、演奏とは別に必要な筋トレもあるのでは?」という疑問が小職の頭の中で引っかかっております。
今回のブログは話を進めるためにその都度説明が必要になり、結果として長くなってしまいました。
なので、時間のない方や、要点だけ手っ取り早く知りたい方向けに、手短に要約いたしますが、筋肉・筋トレに詳しい方が要約だけ見ても、当たり前の内容でしかありません。
あくまで、ミュージシャンのフォーカルジストニアを診続けている鍼灸師が、臨床を通して気づいたこと・気になったこと・疑問に思ったことに対して、考察を書いておりますので、筋肉のスペシャリストさんもジストニアの治療を既に行っている方も、もし宜しければ本文をご覧いただき、小職とは違った考察があればご教示いただき、内容が間違っていたらご指摘いただければ幸いです。
演奏活動を続けつつ、フォーカルジストニアを完全に予防する方法、発症しても確実に一瞬で治癒する方法を見つけるのは難しいと思っておりますが、高確率かつ最短で治す方法を医療従事者として常に探し続けたいと思っておりますので、ご協力いただければ嬉しく思います。
前置きが長くなりましたが、要約スタート<m(__)m>
~~~~~以下、要約開始~~~~~
筋肉の分類として、組成(赤筋、白筋)と形状(紡錘筋、羽状筋)に分けられ、長時間の演奏に適しているのは赤筋かつ紡錘筋になる。
しかし、バスドラムでジストニアを発症しやすい下腿(膝から足首)の筋肉は、強い筋力を発揮するのに適している羽状筋が多数を占めている。
組成に関してはトレーニングの内容次第で、赤筋優位にも白筋優位にも変化させることが可能なので、過酷なライブスケジュールをこなさなくてはならないミュージシャンが、ジストニア予防のために筋トレを行うのであれば、筋肥大を目的とした高重量ローレップではなく、低重量ハイレップの筋トレが適している可能性がある。
~~~~~以上、要約終了~~~~~
要約を書いたので、ここからはフォーカルジストニアを詳しく知りたい方、筋肉・筋トレの知識があまりない方、結局はどのようなドラマーはドラム演奏以外に別途筋トレが必要なのかを、説明していきたいと思います。
⓵フォーカルジストニアの説明
フォーカルジストニア発症の経緯はストレス緊張を含むメンタルの問題、痛みを含めた体調不良、新しい演奏スタイルの習得、楽器の個体やステージの大小を含め、いつもと異なる演奏環境など、いろいろな原因があります。
当院の患者さんでも、いろいろな原因で発症した人を診てきましたが、1日に朝晩2公演をスリーデイズで3日で計6公演や、5~6日連続ワンマンライブなどの過酷なスケジュールをこなしてバスドラムのジストニアを発症した方も数名ほど診てきました。(この演奏スケジュールがジストニア発症の直接のきっかけかは絶対ではありません)
ミュージシャンの方なら想像しやすいと思いますが、上述のライブスケジュールはかなり過酷ですよね!
しかし、同じライブを演奏する他の楽器の方はジストニアを発症せず、ドラマーかつバスドラムの右足に発症という共通点が自分の中で引っかかりました。(もしかしたら発症しつつも無理して演奏していたり、どこかの治療院で施術を受けて治している可能性もあります)
⓶筋肉の分類
まず、筋肉の分類ですが、関節運動を行う際に働く骨格筋、骨格筋と同じく横紋筋だが骨格筋とは違い自分の意志で収縮させることができない不随意筋の心臓と、血管や胃袋、小腸大腸などの平滑筋とに分けられ、ミュージシャンのフォーカルジストニアに関係するのは、もちろん骨格筋です。
なので骨格筋を更に分類しますが、筋繊維形状の違いから紡錘筋と羽状筋に分けられます。(形状の分類としては半羽状筋や多頭筋、鋸筋、多腹筋などもありますが割愛)
紡錘筋は運動速度が速く筋張力が低い動作で働きやすく、羽状筋は速度は遅く大きな筋張力を発揮する動作で働きやすいと言われております。
そして、筋繊維形状以外に筋繊維組成でも特性が異なり、赤筋(遅筋)、白筋(速筋)、桃色筋(遅筋と速筋の中間)と大まかに分けられるのですが、持久力に優れる赤筋は、鉄分を多く含むミオグロビンや、チトクロームという赤い色素を含むミトコンドリアが多く存在するため赤い色になります。
白筋はミオグロビンやミトコンドリアをあまり含まないので白くなります。
白筋で羽状筋なら強い力を発揮し、赤筋で紡錘筋なら持久力に優れているとイメージしやすいですが、羽状筋で赤筋多めとか、紡錘筋で白筋多めの筋肉ももちろんあるので、この分類はアスリートやボディビルダーほどには意識しすぎなくても良いかもしれません。
話しはそれますが、小職は小学生の頃、少年ジャンプのプロレス漫画「THE MOMOTAROH」を読んで、桃色筋肉は白筋と赤筋の両方の特性を備えた最強の筋肉と信じていたのですが、そんな都合の良い筋肉ではなかったと大人になって知りました!
筋繊維形状に関しては、先天的な物なので、例えば上腕二頭筋は紡錘筋ですが、力を発揮しやすい羽状筋に変えたいと思っても不可能です。
しかし、組成に関しては先天的な側面もありますが、トレーニングや生活スタイルによって、赤筋が多めにも白筋が多めにも変化させることが可能という論文も発表されております。
同じ遺伝子情報を持つ一卵性双生児において、持久力トレーニングを継続的に行った双生児は、行わなかった双生児に比べて赤筋が多くなって、持久力も高くなっているという内容です!
詳しく知りたい方は下記URLより論文をご覧くださいませ。
https://www.researchgate.net/publication/326398362_Muscle_health_and_performance_in_monozygotic_twins_with_30_years_of_discordant_exercise_habits
③バスドラムに関係する足の筋肉
足は膝から上の大腿と、膝から下の下腿、足関節から足趾までの足部に分けられますが、下腿の筋肉によるジストニア症状を一番多く診ております。(大腿四頭筋やハムストリングス、内転筋など大腿の筋肉のジストニアや足の裏の筋肉のジストニア症状も診ていますが、下腿の筋肉のジストニアから病変部位が広がったように感じてます)
バスドラムのヒールアップ奏法で最も使うのは、足関節を底屈(屈曲)させる屈曲筋群です。
ふくらはぎで一番大きい筋肉の腓腹筋は足関節底屈に関わる紡錘筋で、腓腹筋の補助的な働きをする足底筋も紡錘筋です。
足関節底屈に関わる大きな筋肉が紡錘筋ということは心強く感じられそうですが、腓腹筋も足底筋も膝関節と足関節の二つの関節を跨ぐため、座って膝関節が屈曲した状態では、筋肉が弛む状態になり少し働かせづらくなります。
それでは、膝関節を跨がず、足関節の底屈に作用する筋肉はというと、長短腓骨筋、ヒラメ筋、長趾屈筋、長母趾屈筋、後脛骨筋が挙げられますが全て羽状筋です。
そうなんです!
小職なりの仮説ですが、下腿の底屈筋は疲労の蓄積によって働きが低下して、働けなくなると他の筋肉を無意識下に使って、少しずつフォームが変わったり、普段と違う筋肉の力みを生じてジストニアを発症してしまうのではないだろうか。
要約に書いているので、何をいまさらと言う感じですね(-_-;)
もちろん、足関節背屈(伸展)に関わる筋肉のフォーカルジストニアを患う方も多く診ております。
伸筋に属する筋肉の中で羽状筋は、長趾伸筋、長母趾伸筋。紡錘筋は前脛骨筋が挙げられます。
前脛骨筋は足関節の背屈に働くので、ヒールダウンでの演奏では重要な働きをしますが、ヒールアップではそれほど酷使しないかと思います。
ちなみに、ヒールアップでもメタル等のように早いテンポで叩き続ける際は酷使しますが、そもそも人間の身体は音楽の限界に挑戦するために作られておりません。
最近の若者の音楽を聴いていると、男性ボーカルが女性ボーカルの音域で歌ったり、楽器隊が一小節内に一音でも多い音を詰め込んだりしていて、過去の音楽に対する進化や新しい音楽の追及としては分かりやすいのかもしれません。
しかし、若い頃に作った一曲がヒットして、その一曲と数曲程度を対バンライブや夏フェスなどで演奏するのは良いですが、ヒット曲に恵まれて中堅どころの年齢になり、ワンマンライブを年中続けるようになった際には、鉄板のヒット曲が自分の首を絞める結果になることも頭の片隅に置いておいた方が良い・・・と考えるのは中年だからなのでしょうね(-_-;)
④筋トレ
前述のとおり、演奏に使う筋肉を一番効率よく鍛える方法は、必要最小限の筋力で演奏することになります。
なので、それほど過酷でない演奏内容かつ一般的なライブスケジュールでの演奏活動でしたら、ジストニア予防のために演奏以外の筋トレは必要ないかと思います。筋トレよりもライブ前後のコンディショニングに注意しましょう!
しかし、1日2ステージとか、連日ライブを行うようなバンドの方、人間の限界に挑戦するような演奏内容の方は、下腿の羽状筋群の筋持久力を高めるために、赤筋繊維を増やす低重量ハイレップのトレーニングを行う方が、ジストニア予防につながりやすいのではないかと思います。
*レップは筋トレ界隈では普通に使う用語で、反復を意味するrepetitionの略です。低重量ハイレップの目安は、1回持ち上げるのが限界の重さ(1RM=repetition max)の50%の重さで、20回くらい反復です。例としては、50Kgの荷物を背負って1回だけスクワットをできる方の場合、25Kgの荷物を背負って20回位の限界までスクワットを行います。
筋トレの種類には筋肉の収縮方法にも違いがあり、等張性収縮(アイソトニック)・等尺性収縮(アイソメトリック)・等速性収縮(アイソキネティック)と分けられ、等張性収縮は更に求心性収縮(エキセントリック)と遠心性収縮(コンセントリック)に分けられます。
この中で、筋持久力の向上にどの収縮方法が良いかと言うと、等張性収縮になります。等速性収縮はそもそも特殊なマシンが必要なので、小職は行ったことはありません!
最大筋力の向上を目的とする場合は、高重量低レップのエキセントリック収縮かつ時間をかけるのが最も効果的と言われてます。この場合は1RMの80%の重さで2~3回が目安です。
前述の足関節底屈筋群(長短腓骨筋、ヒラメ筋、長趾屈筋、長母趾屈筋、後脛骨筋)を鍛える方法ですが、全て底屈筋とは言え役割が少しずつ異なるので、一つの筋トレで全ての筋肉に効かせるのは難しいです。
腓骨筋や長趾屈筋へのアプローチとしては、足関節の内反底屈で足の第五趾(小指)側に荷重をかける方が、より効かせられますし、長母趾屈筋に効かせたければ足の第一趾(親指)側に荷重をかけた方が効きます。
このように一つ一つの筋肉の起始停止と走行を考えて、働きを意識しながら筋トレを行うのが理想なので、可能な方はゴムチューブなどを使って行ってみてください。
上述の筋トレ方法を見て、「難しい!分かりにくい!」と感じた方は、下記の方法を試してみてください。
ドラムの椅子に座って、両腕でしっかりと右膝に体重をかけて、足関節を底屈して踵を持ち上げる。
ツーバスの方は右足だけでなく、左足も行ってください。
パートナーさんや子供がいらっしゃる方は、膝に座ってもらうのも有りかとおもいますが、自分が嫁に乗ってもらったのを想像すると、江戸時代の拷問「石抱き」のようになってしまいました(゚Д゚;)
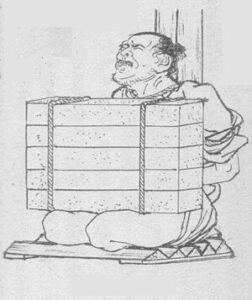
ちなみに、膝を曲げずに立位で踵をあげれば、二関節筋の腓腹筋と足底筋にも効かせられます。
⑤最後に
今回のブログは約7000文字という過去最長の長さで、ブログを久しく書いていなかったこともあり、不慣れになった作業は正直いって疲れました!(過去のブログは基本的に500文字程度に収めてました。)
3回位に分けて投稿することも考えましたが、最初に要約を書いておいて小出しにするのも何となく間抜けな気がして、もっと脇道にそれた漫画小話など(グラップラー刃牙とか)も挟みたい衝動にかられつつ抑え込んだのですが、プロレス漫画「THE MOMOTAROH」に関しては、衝動を抑えきれませんでした(笑)
しかし、筋肉にそれほど興味もないのに最後まで読んでくださった方、たぶん私以上に疲れたでしょう、大変お疲れ様でした。
そして、ありがとうございました!
こんだけ長々と「筋肉だ」「筋トレだ」と書いておいてなんですが、ジストニアは筋力・筋持久力だけで予防できるものではありません。
過酷だからといえど若いうちは仕事を選ぶ余裕もないでしょうし、有名なアーティストのサポートの話が降ってわいたら多少無理をしてでも仕事をつかみたいでしょう、性格の悪いリーダー格のバンドメンバーと上手く折り合いを付けなくてはならないこともあるかと思います。
たった一度の人生です、好きで始めた音楽がジストニアによって苦痛になってしまわないよう、まずは発病しないように予防できるところは積極的に予防を心掛けて、無理なく楽しく音楽と向き合いましょう!
気を付けていたのにそれでも発病してしまった方、大丈夫です!!
弊院の患者さんで完治した方の中には、「ジストニア発病前は出来なかった演奏ができるようになれた」、「ジストニアを克服するリハビリのお陰で発病前よりも音が良くなった。ジストニアになってよかった」、そうおっしゃられるトッププロの方も複数診ております。
小職が開業した10数年前と比べて、インターネットでもジストニアの情報は増えて、ジストニアの治療・施術を行う医療機関も増えてきましたが、臨床経験がないのに、「診れます・治せます」を謳う治療院や、患者さんにサクラになってくれるよう依頼する治療院の話などチラホラ耳にしています。
病院の医者だから大丈夫かと聞かれたら、手根管症候群や肘部管症候群と誤診して、無駄な手術を行われた患者さんも何人か診ています。手術で治らなかったと執刀医に訴えても、「じゃー脳外科手術の病院をご紹介しますね」という無責任な対応。
*この誤診は手術後に症状が変化したわけではなく、手術前の状態を診なくても、患者さんの話を2~3分程度聞けば明らかに症状が違うので誤診とわかるレベルです。
医者としてのプライドから「病気の原因・病名が分かりません」の一言が言えないのか、病院の方針で診療報酬を稼ぐためにオペの件数を増やしたいのか、患者さんの身体に平気でメスを入れるような医者も意外とそこらにいます。
弊院では、初回施術時に患者さんにお伝えしますが、「3回施術を受けても全く変化が無ければ、他の鍼灸院もしくは他の施術方法を検討した方が良い。」これは、他所の治療院に通っている方にも推奨します。
施術後に良い変化が現れても次の来院時に元に戻ってしまう場合は、リハビリで無理をしてしまったり、リハビリ方法を間違えてしまっている可能性も考えます。
しかし、初診で変化が出ない場合は、2回目の施術では違う方法を試したり、刺激量を増やしたりして、それでもダメで3回目の施術も施術内容に変化をつけても変化がない場合、正直に申し上げて、弊院含めてその治療院の施術内容ではご自身の症状に変化が起こる可能性は低いです。
その説明を患者さんご自身が理解したうえで、それでもご要望があれば弊院ではできる限り他の方法を考えたり、患者さん自身が希望する施術方法なりを行わせていただいております。
お金も時間も貴重です。無駄にしないよう、いろいろとトライしてみましょう!
最後の最後に!!
小職が投稿しているブログやYouTube動画が、ジストニア症状で悩んでいる方の希望につながり、これからミュージシャンの治療家を志す後輩達や現役でミュージシャンの治療を行っている先生が、より良い予防方法・施術方法をミュージシャンに提供するための参考になれば何よりです!
参考文献⓵chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.jstage.jst.go.jp/article/rika/33/6/33_917/_pdf
参考文献⓶
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.jstage.jst.go.jp/article/rigaku/23/7/23_KJ00001307810/_pdf


